京都体験
最新コンテンツ・イベント情報
-
梅は二千年前に日本へ伝わり、兵糧、家庭薬、嗜好品として時代とともに形を変えながら家庭で手作りする独自の文化が育ちました。梅体験専門店「蝶矢」は日本の梅文化を現代的なスタイルで提供し、「大切な人とのつながりを育む文化」として世界へ発信していきます。
-
京都市観光協会が運営する「HANDS FREE KYOTO」は、観光客が快適に京都を巡るための手ぶら観光情報をまとめたサイトです。
大きな荷物を宿泊施設へ送る配送サービスや、一時的に預けられる窓口・コインロッカーの情報を、京都駅周辺のマップと共に分かりやすく紹介しています。
手荷物による公共交通機関の混雑を防ぎ、誰もが楽しめる観光を目指します
-
SPA PASS KYOTO とは
京都市内の温泉10施設(2025年10月1日時点)から選んで「湯めぐり」をすることができる電子周遊パスです。異なる3施設を周遊できるよう設定した電子チケットを温泉施設に提示することで、各地に点在する京都市内の温泉施設をめぐることができます。また、温泉施設の食事やカフェなどの付帯施設の利用促進にも取り組み、様々な角度で温泉の利用をご提案しています。
【実施期間】
発売期間:2025年10月8日(水)~2026年3月31日(火)利用期間:2025年10月8日(水)~2026年3月31日(火)
※施設指定プランは、ご利用日の3日前 までにご予約ください。
※お支払いは、クレジットカードのオンライン決済のみとなります
※お出かけの際は、便利な市バス・地下鉄をご利用ください
-
より気軽に、より楽しく!
日本酒好きな方はもちろん、日本酒初心者の方や、
日本酒を通して日本文化を体験したい観光客の方々にも、
日本酒を通じてわくわくと驚きを体験してほしい。
そして、この場所が日本酒ファンの輪を広げるきっかけとなることを目指しています。8種類の日本酒を試飲し、自分の好みを見つける。
好みのお酒をブレンドすることで世界に一つだけの味わいの日本酒がつくれる体験施設。また、つくったお酒は隣の建物の酒造室にて瓶詰めしたものを、その日に持ち帰りができる他にはない日本酒体験施設です。さぁ、あなたも自分好みの日本酒を、
「世界でひとつだけの味わい」を自分の手で作ってみませんか?
※20歳未満の方、及び、ご来店にお車や自転車を運転される方のご飲酒は固くお断りいたします。
▼個人のお申込みは、こちらから
日本酒のブレンド体験 ~My Sake World 京都河原町店~
▼団体のご相談は、メールにてお問合せください。
LINK KYOTO事務局(link_kyoto@jtb.com)
-
宇治のシンボルである宇治橋と太閤堤跡、莵道稚郎皇子御墓を結ぶ、歴史軸上に位置します。その歴史を感じることができる史跡、庭園、広場、お茶と宇治のまち交流館「茶づな」では、宇治の時の流れを展示と映像を通し、また茶摘みや抹茶づくりなどさまざまな体験プログラムを通して、まちとひと、歴史・文化をつなぎ、宇治の観光・まち歩きが楽しくなる魅力を発信します。
引用:茶づなホームページより
動画はこちらから:
-
光と音に包まれ、夜に輝く植物たちの世界へ
日本最古の公立植物園として2024年に開園100周年を迎え、期間限定で夜間開放される京都府立植物園では、昼間とは異なる植物たちの神秘的な別世界に包まれます。日本最大級の観覧温室に足を踏み入れると、光や音、セットデザイン、プロジェクションによって彩られた豊かな緑が広がり、生命力あふれる植物の輝きを目にします。
4つの異なるゾーンを巡りながら、植物の呼吸やささやき、夜に浮かび上がる多彩な表情を五感で感じ取ることができます。
光と音が織り成す幻想的な世界で、新たな植物の魅力と自然とのつながりを育む没入体験をぜひお楽しみください。
-
①「絹の白生地資料館」の見学(所要時間:約15分)
絹の白生地資料館は、着物の白生地専門の資料館です。生糸で織り上げられた生地を後から染める後染め(染めの着物)用の白生地を、これまで伊と幸が織り上げてきました200種3000柄の中から厳選した約50種を展示しております。各産地や糸の種類などの違いにより様々な特徴を持った白生地を実際に手に触れ、その風合い、美しい光沢をご覧いただけます。国内養蚕農家による繭生産や、着物に必要な繭量の知識など、1反の白生地が出来上がるまでの工程をご紹介します。
②「手織機」の体験(所要時間:約15分)
社内インストラクターが手機機の実演を行い、経糸と緯糸の仕組みなどをご説明します。その後、実際に手織機を使った織物体験をお楽しみください。
③金彩友禅のワークショップ(所要時間:約1時間30分)
着物で使う高級素材、正絹生地に友禅技法で染料を色挿しし、金彩加工で仕上げる体験をお楽しみいただきます。社内講師が丁寧に指導しますので、初心者の方でも安心してご参加いただけます。完成した作品は額に入れてお渡ししますので、インテリアとして思い出をお持ち帰りいただけます。

-
大正元年創業の老舗旅館「炭屋旅館」
京の中心部である三条麩屋町でひときわ目を引く、落ち着いた数寄屋造りの佇まい。客室や茶室から望む中庭では、四季折々の美しい季節を感じていただけます。炭屋旅館での抹茶体験では、抹茶のたて方 飲み方を教えてもらい、自分で点ててみたり、家族同士・友人同士で点てたお抹茶を飲みあったりと、楽しいひとときを過ごす事が出来ます。
炭屋旅館は、裏千家とゆかりの深い「茶の湯の宿」としても有名。館内には5つの茶室があり、なかでも有名なのが「玉兎庵」。兎年であった先々代にちなんで裏千家十四代家元・淡々斎により命名されました。
本プランは、グループ様ごとの貸切プランとなります。正座が苦手な方には、椅子席もご用意がございます。この機会に、ぜひ 炭屋旅館へおこしください。
貸切体験プライベート体験Sumiya RyokanMatcha ExperienceKYOTO京都体験tea ceremony老舗抹茶茶室LINK KYOTO歴史体験京都本物京都文化伝統文化
-
京都でも有名な芸妓であった「上羽秀(うえばひで」が、東映のプロデューサーをしていた夫の‘俊藤浩滋(しゅんどうこうじ)’と娘の‘高子’と共に余生を暮らすために建てた和邸宅「岡崎庵」
モダンな内装と当時としては珍しい総檜の能舞台付きという贅沢な作りで、窓からは平安神宮の鳥居や大文字山の眺めが一望。
この優雅な気分になる場所で、能舞台で舞う舞妓さんの舞鑑賞とお食事を楽しむ贅沢プランです。
各時間1組限定ですので、鑑賞後には記念撮影や歓談と舞妓さんを独占できる時間は、京都の忘れられない思い出になることでしょう。
※こちらのプランは、リクエスト予約となっております。ご希望の日程予約可否については、WEBにてお申込み後、事業者へ確認後にメールにてご連絡させていただきます。
-
京都発明協会は、明治34年の設立以来、100年以上にわたって地域の産業と知的財産を支えてきました。本プログラム「京都発明教室」では、京都で生まれた歴史的発明から、私たちの暮らしを支える最新技術までを題材に、発明の仕組みや知的財産の役割を楽しく学びます。
講義と体験型ワークショップを通して、子どもたちが自ら問いを立て、答えを探し、未来の課題解決のヒントをつかむ探究型の学習プログラムです。伝統の知恵と現代の技術を結び付け、発想力と多角的思考を育みます。





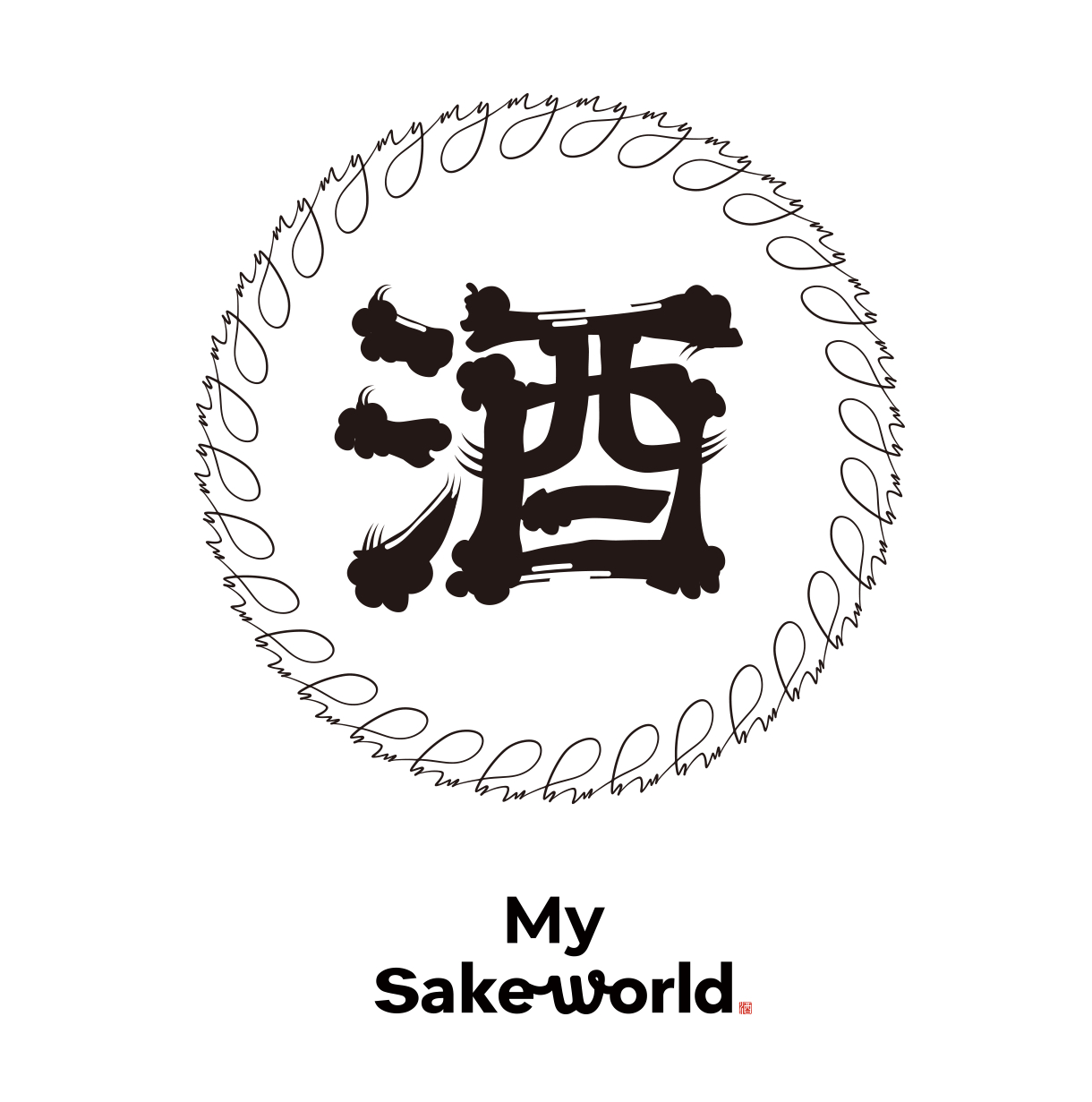










 京都の体験
京都の体験 お電話でのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ